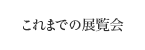![[会期]2020年1月18日(土)~ 3月1日(日) 新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡散防止のため、会期終了を3月15日から変更いたしました。 [休館日]毎週月曜日 (ただし2月24日は開館)、2月25日(火) [開館時間]午前10時~午後4時30分(入館は午後4時まで) [入館料]一般1,000円、大学生・高校生および障害者手帳をお持ちの方(同伴者1名含む)700円 中学生以下無料 ※20名様以上の団体は200円割引](images/20200118_title_02.png)
中国宋代(960~1279)の陶磁器は「宋磁(そうじ)」と称され、中国の工芸文化のひとつのピークを示すものとして世界的に評価されています。2020年は、近代における宋磁蒐集の契機となった北宋の町「鉅鹿(きょろく)」遺跡と磁州窯(じしゅうよう)の陶器の再発見からおよそ100年にあたります。
磁州窯は河北省南部に位置し、五代(10世紀)以降現代まで日用の器物を大量に生産した民窯です。白化粧(しろげしょう)や黒釉の技法を基本に、独特の「掻落(かきおと)し」と呼ばれる彫刻的な文様表現、鉄絵(てつえ)や紅緑彩(こうりょくさい)(赤絵)、三彩や翡翠(ひすい)釉などを用いた多種多彩で装飾性豊かな陶器を生み出しました。また同様の製品を焼造する生産地は、河南・山西・山東・安徽・陝西といった華北地域一帯に広がり、またその技術は国境を越えて契丹(きったん)族の遼(916~1125)やタングート族の西夏(1038~1227)にまで伝わっていきました。
本展ではまとまって公開されることの少なかった館蔵の磁州窯とその周辺の陶磁器(磁州窯系陶器)を紹介します。あわせて国宝「曜変天目(稲葉天目)」をはじめとする宋磁の名品を展示いたします。
※鉅鹿…河北省南部の町。北宋・大観2年(1108)、漳河(しょうが)の氾濫により一挙に泥土に埋没し、1920年前後に遺跡が発見され、大規模な発掘がはじまった。磁州窯陶器をはじめとする大量の陶磁器や建築址などが出土し、「東洋のポンペイ」と呼ばれた。
磁州窯の陶器を特徴づけるのは、泥状に溶いた白土を器の素地に掛けて白い器面(白地(しろじ))を作る「白化粧(しろげしょう)」と多量の鉄分によって発色する黒釉や鉄絵具(てつえのぐ)の技術、そして器面を彫り込んで化粧した表面と下地の色彩のコントラストによって文様を浮き立たせる掻落(かきおと)しや線彫りの装飾技法です。唐~宋時代、希少な白い磁器土を使う白磁は高級品でした。本来は鉄分が多く、焼くとグレーになってしまう粗悪な陶土を使って、高級な白磁の色味に近づけようと行われたのが白化粧の技法です。さらに北宋中期以降には白地に鉄絵具を塗って掻落す「白地黒掻落(しろじくろかきとし)」や鉄絵具で直接文様を描く「白地鉄絵(しろじてつえ)」が登場し、白黒の強いコントラストの装飾へと発展しました。磁州窯で作られた白化粧と黒釉の陶器(白地陶器と黒釉陶器)は、生産コストの安さ、技術的模倣の容易さ、色彩のコントラストを強調した美しさなどから華北一帯へと広まっていったのです。

磁州窯の代名詞といえるのが本作に見られる「白地黒掻落し」の技法である。この文様は筆描による絵画ではなく、白地を覆うように鉄絵具を塗った後、文様を線彫りして背景となる部分の鉄絵具だけを掻落し、白地を出すという繊細かつ手間のかかる彫刻的技法によっている。白と黒の強い色彩の対比による文様表現が宋時代の他の窯には見られない最大のセールスポイント。文様の牡丹は「富貴」のシンボルで、雲のような如意頭の形は「意のままになる」ことを意味する。磁州窯の枕の屈指の名品である。

磁州窯系の陶器において白化粧と対をなす重要な技法が黒釉を用いた装飾である。その中には、部分的に白泥を使うものや本作のように白化粧陶器同様に線彫りや掻落しによって色彩のコントラストを作り出す作品が知られる。近年の研究により本作は山西省北部の窯で焼かれたものと考えられている。

北宋時代に続く金時代には「白地黒掻落し」の技法が簡便化され、彫刻的技法によらず、筆に鉄絵具を含ませて白化粧の地に直接文様を描く技法に発展した。文様にはやわらかさや軽快さが加わっている。この「白地鉄絵」は透明釉の下に文様を絵付けする「下絵付(したえつけ)(釉下彩(ゆうかさい))」の技法であり、酸化コバルトを使った青い文様の染付(そめつけ)(青花(せいか))に先駆けたものといえよう。
磁州窯では「技のデパート」と称されるほどさまざまな施文技法や施釉技法が開発されました。白化粧と黒釉だけではない色トリドリのワザの数々、その一端をご覧いただきます。

三彩釉によって青々とした葉をもつ白い蓮と蒲(がま)の穂のブーケがあらわされる。蓮は幸福な結婚と子孫繁栄のシンボル。新婚夫婦向けの枕だろうか。ブーケの背景は、白地を掻落して現れた赤茶色の素地に緑釉を掛けることによって黒く発色している。

透明釉を掛けて高温で焼いた白地陶器の上に赤や緑、黄色の釉薬で文様を描いて再度低い温度で焼きつける、いわゆる赤絵(あかえ)(上絵付(うわえつけ)/釉上彩(ゆうじょうさい))を世界で初めて行ったのが磁州窯である。明代以降に江西省の景徳鎮窯(けいとくちんよう)で隆盛していく五彩磁器(ごさいじき)の先駆的なものであり、かつては日本で「宋赤絵(そうあかえ)」と呼ばれ、芸術家やコレクターたちに人気を博した。

白地鉄絵の仕上げに、透明釉でなく低温焼成で青緑色を呈する翡翠釉(孔雀釉(くじゃくゆう))を掛けた作品。素早く軽快な筆致で湧き上がる雲のような菊花の文様が描かれている。
北宋(960~1126)・南宋(1127~1279)の約300年にわたる宋代のやきもの、すなわち「宋磁」は、約8000年の歴史をもつ中国陶磁の最高峰と称されています。宋代には著しい発展を見せた各種の産業や文化・芸術とともに、陶磁器もより実用性や耐久性に優れ、かつ洗練された美観をそなえる工芸へと進化しました。宋磁はいずれも緊張感のある端正な造形で、釉薬の美しさを引き立たせるための精緻な彫刻や型押しの文様、花形や瓜形の器形といったデザインに工夫がみられます。宋磁の洗練された美しさは、後世の陶工たちが追い求める規範となっていきました。

河北省の定窯(ていよう)は華北を代表する白磁の名窯で、その製品は温かみのある「牙白色(げはくしょく)」(アイボリーホワイト)の釉色と、薄い器胎に片切り彫り(かたぎりぼり)(刻花)で施された流麗な文様が特徴となっている。本作は茶の湯の水指として加賀藩主前田家に伝わった鉢で、瓜形に刻みをつけた器に蓮の花の文様が彫り込まれている。

陝西省の耀州窯(ようしゅうよう)は、独特の透明感あるオリーブグリーンの青磁を生産した華北青磁窯の雄。片切り彫りによる浮彫り風の文様を密にあらわした本作は、耀州窯では極めて稀な枕であり、世界的に知られる名品。

宮廷専用の陶磁器を焼く窯を官窯(かんよう)という。南宋時代、首都・杭州(浙江省)に置かれた官窯ではただ青磁のみが焼かれ、飲食器や祭礼の器などとして宮廷に納められた。青緑色の澄んだ釉色と複雑に入り組んだ釉薬のヒビ「貫入(かんにゅう)」が特徴で、本作は古代青銅器の鼎の形を写したもの。

「天目」は北宋時代の喫茶法(日本の抹茶の源流となった「点茶法(てんちゃほう)」)に合わせて生まれた喫茶専用の碗を指す日本での名称。そのうち福建省建窯(けんよう)産の器「建盞(けんさん)」は皇帝にも用いられた記録があり、曜変天目は近年中国杭州の南宋宮殿跡付近で破片が発見されている。本作は徳川将軍家から春日局を通じて淀藩主稲葉家へと伝わったため、「稲葉天目(いなばてんもく)」とも呼ばれている。
1.講演会
「磁州窯と磁州窯系諸窯、そしてその影響の軌跡」日時:2月22日(土) 午後1時30分開演
講師:守屋雅史氏(神戸松蔭女子学院大学教授)
会場:当館地階講堂
定員:120名
聴講料:無料(ただし、当日の入館券が必要)
申込方法:当日、開館時より整理券配布(1名様につき1枚)
※整理券の番号順にお入りいただきます。
2.河野元昭館長のおしゃべりトーク
「めでたい絵 饒舌館長口演す ―磁州窯発 江戸絵画行き―」日時:2月1日(土)午後1時30分開演
講師:河野元昭(静嘉堂文庫美術館館長)
会場:当館地階講堂
定員:120名
聴講料:無料(ただし、当日の入館券が必要)
申込方法:当日、開館時より整理券配布(1名様につき1枚)
※整理券の番号順にお入りいただきます。
3.陶芸ワークショップ
「掻落しで陶器に絵を描く」日時:2月16日(日)
A(午前の部):午前10時30分~午後0時30分
B(午後の部):午後1時30分~午後3時30分
会場:当館地階講堂
定員:A・Bいずれも定員20名
内容:磁州窯を代表する装飾技法「白地黒掻落」で皿に文様を描きます。
講師:小山耕一氏(東京竜泉窯)
参加費:2,500円(入館料別)
申込方法:事前申し込み制となります。詳細は順次「お知らせ」ページに掲載していきますのでご確認ください。
4.静嘉堂コンサート
「100万人のクラシックライブ」日時:3月7日(土)午後2時開演(予定)
参加費:1,000円(入館料別)
申込方法:事前申し込み制となります。詳細は順次「お知らせ」ページに掲載していきますのでご確認ください。
会場:当館地階講堂
定員:100名
※詳細はこちらをご覧ください
5.列品解説
展示内容・作品について担当学芸員が解説します(展示室または講堂にて)。午前11時~:1月25日(土)、2月29日(土)
午後2時~:2月13日(木)、3月12日(木)